子供をもつと、何かを聞かれた時にちゃんと答えられるのかという焦りを多少なりとも感じます。
我が家のちびちゃんはまだ言葉もままならないけれど、3歳にもなってしまえば、きっとそういった問題がたくさん出てくるだろうと容易に想像がつきます。
そのうちの一つが、美術って何?という問いです。
私は美術大学を卒業しているし、ある程度学んできたつもりなのですが、体系立てて美術を語ることなんてとてもできません。
そこでもう一度、体系立てて美術が語られていることで有名な普及の名著、ゴンブリッチの『美術の物語』を読んでみようと思い立ちました。
この記事は、ゴンブリッチの『美術の物語』を読みながら私がメモをした内容をまとめたものです。
おそらく、1記事では終わらず、何記事かに跨ったものとなる予定ですので、お付き合いいただければ嬉しいです。
この本の目的とは何か

この本を手に取る人は、ゴンブリッチがいうように、作品を鑑賞する上での“道案内のようなもの”があったらいいなと思っている人も多いでしょう。
実際に、そういったことのためにまとめられた本とも言えます。その言葉通り、分厚い見た目とは裏腹に、読みやすい文章と大きくて大量の図版たちがそれを物語っています。
そしてまえがき部分には、この本の明確な目的や目標が書かれています。それは、
〜読者に美術史の流れをわかってもらい、美術を深く味わってもらいたい
E.H.ゴンブリッチ 『美術の物語』p.8
というものです。
ゴンブリッチはもう少し野心的な目標として、
作品の歴史的な背景を考えること、そしてそれによって、作り手の芸術的なねらいを理解すること
E.H.ゴンブリッチ 『美術の物語』p.9
というものも挙げています。
それぞれの美術作品には、作者はもちろん、その時代の背景や作られた理由などが存在します。それらを知ることで誤解や検討はずれの批評を防げると考えているのです。
そして、作り手の芸術的なねらいというのは見定めるのが難しいように思うけれど、ゴンブリッチは一つの要素を理解への手がかりとして提示しています。それは、先代の常識に対する反発の要素です。
だれでも、親たちの世代の常識に対しては、どこかで反発を感じるものだ。〜人とちがったことをやりたいという衝動は、芸術家にもとえられる〜根源的な要素でもない。しかし、それがまったくかけていることはめったにない。だから、芸術家たちがどこに差を出そうとしているのかがわかると、過去の芸術を理解する道が、意外と簡単に開けるものだ。
E.H.ゴンブリッチ 『美術の物語』p.9
変わらない人間の普遍的な衝動をベースとすれば、その作品の作者が何に対して反発をしているのかを紐解いていくと、自然と美術の歴史の流れ、もっというと人間の価値観の歴史が見えてくるのかもしれません。
“美術“そのものについて

美術ってなに?と息子に問われることを恐れている私がとりあえず読むべきは、序章のようです。
ここでは、美術そのものについて、それはなんなのかを紐解いていきます。
人はこれまでの歴史の中で、いろんなものを作ってきたし、今も作り続けていますよね。それら全て、人の作り出すものが“美術“なのだとしたら、どうでしょう。これはデザインなのだとか、いろんな方面から指摘が入りそうです。
ゴンブリッチは、
これこそが美術だというものが存在するわけではない。作る人たちが存在するだけだ。
E.H.ゴンブリッチ 『美術の物語』p.15
と最初に明言しています。“美術”というのは、普遍的な概念ではないのです。
作品を素晴らしいと思う理由は人それぞれで、その絵が可愛いとか、その絵がとても綺麗だからとか、人によっていろんな答えがあると思います。
しかし、絵のモチーフとして、可愛いとか綺麗とか、そういう好印象なものばかり求めるのは、少し注意すべきとゴンブリッチは言います。絵の素晴らしさは、モチーフのかわいさ、美しさにあるのではなく、その画家が感じていたものを感じ取ることによって素晴らしいと思うのです。
もちろん、何が美しいと感じるのかは人それぞれですが、細密な描写が好きだからといって、キュビズム時代のピカソのようにずれた描写を批判して良いことにはなりません。
もし、そういったズレた作品を目の当たりにした場合に、下記の2つの点に注意するといいそうです。
- 変形するのはそれなりの理由があった
- 不正確な描写だからと非難しない
つまり、不正確な描写やズレた描写は技術の拙さを表す要素ではなく、何か意図的なものだったのではないかと疑うことが重要と指摘しているのです。
このように、自分の持っている先入観を捨てて、新鮮な気持ちで対峙しなければ、優れた作品は楽しむことができないでしょう。
逆に言えば、作品によって使われる言語が違うことを理解することによって、きっと以前より作品の見方が広がるはずです。
最後に、ゴンブリッチの指摘していた意外な言葉をご紹介します。
それは“これで決まり”という言葉です。
作品は、ある特定の状況と目的に合わせて制作され、作り手が“これで決まり”と決断してきた結果生まれてきました。
つまり、“これで決まり”というその作者の思いが今対峙している作品に現れているのだとしたら、その言葉の意味を理解しようと努めることで作り手が求めていたものに近づくことができると言います。
さて、ここまででかなり息子に質問された時に答えられるような重要な情報が盛りだくさんでしたが、実はまだ本章に入っていません。
この本は全28章と、なかなか長い道のりになりそうですが、できるペースで読んでいきたいと思います。次は第1章からの記事となりますので、もしお付き合いいただけるならぜひ読んでみてください。
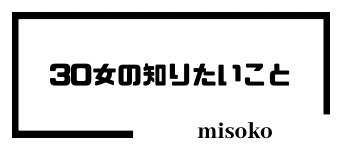


コメント