この連続記事は、私がいつか息子に聞かれるかもしれない“美術って何?”という問いに答えるべく、改めてゴンブリッチの『美術の物語』を読み直し、それに備えるためのものです。
序章編では、この本の目的や、美術という概念そのものについてみてきました。
もし気になる方は、こちらのページからみてみてください。
今日はついに本編に入っていきます。第1章編です。
美術は実用的なものだった?

第1章で取り上げているのは、美術がどう始まったかというテーマです。
そのため、章全体を通して未開の人々や昔の文明などを取り上げています。
もし美術という言葉が、家や寺院を建てたり、絵や彫刻を作ったり、文様を織ったりする活動を意味するというのなら、美術を持たない民族などひとつもない。
G.H.ゴンブリッチ 『美術の物語』p.39
今の私たちの感覚になんとなく根付いてしまった、美術は美術館や展覧会で見られるもの、高価で貴重なものという印象は、最近できたものなのです。

例えば建築、これらは住むためだったり、礼拝をするため、みんなで集まるため等、必ずある種の役割を持って作られてきたものです。
建築にとっての“良さ”というのは使いやすさであることと同時に、作り手が“これでよし”と思った感覚によって出来上がるものでした。
これは絵画も彫刻も同様で、何かしらの役割をもつということが前提としてあったのです。
絵画や彫刻に実用的な役割があるというのはどういうことなのでしょう?
私たちがそれを想像するのにわかりやすい例があります。
それは、自分の推しであるアイドルや俳優などのうつった写真を前にする時です。
果たして、その写真を破いたり、傷つけたり、上から落書きをしたりできるでしょうか。きっとできないと思います。
これはつまり、ただの紙に対してのことでも、写っている人に対して失礼なことをするような感覚が残っているということです。
この例を用いれば、
“なぜラスコーの壁画の奥深くに、わざわざ動物の絵が描かれているのか?“
ということを読み解くことができるはずだとゴンブリッチは推測します。
〜原始時代の狩人たちは、獲物の絵を描くだけで、そして多分、それを槍や石斧で打ちつづけるだけで、本物の動物も自分達に屈服するだろうと考えていたのだ。
G.H.ゴンブリッチ『美術の物語』p.42
つまり、原始時代の人々にとっての絵画や彫刻は、表された本体が宿る媒体として機能していたのではないかということです。
技術の拙さは誤解?

ここまで、元々美術が実用的なものとして機能していたというゴンブリッチの考えを見てきました。
しかし、実用的な役割を持つのであれば、未開文明の美術に対して、なぜもっと実物に迫った描写にしなかったのかと疑問をもつ人もいるかもしれませんね。
事実、ラスコーの壁画は原始時代といえどかなり真に迫った描写に思えるけれど、それ以降の未開文明を見渡すと、もっと歪であったりわざと歪ませた表現が目立ちます。
もっと後の世代の文明であれば、きっと技術を発達させられたはずなのになぜなのでしょうか?
ここでゴンブリッチが忠告していることがあります。
この本を通して私が語ろうとしているのは、美術における技術の進歩の歴史ではなく、美術についての考え方や社会的な条件の変化の物語なのだ。
G.H.ゴンブリッチ『美術の物語』p.44
ゴンブリッチは、未開の人々だからといって工芸の知識が未開なわけではなく、精通しているものもいた中で、わざわざ歪で特異なように見えるものを作ったのには理由があったというのです。

もともと、未開文明における絵画や彫刻は、美しさを狙ったものではありません。
儀式用に作られたものが多く、神話や言い伝えに登場する妖怪や神々を表すためのものも少なくありません。
つまり、未開の人々は、それを表すためにはどの要素を表現すれば十分なのかを熟知していたのです。
私たちからみれば不気味に見えるそれらの像たちの要素一つ一つには、必ず重要な意味があります。
それをなぜ作ったのか、その精神に迫ることで、実は文字の始まりとも関連するその民族の思考にも触れることができるはずだとゴンブリッチはいいます。

確かに、私たちが使っている漢字も元々は象形文字で、それはかなり絵に近いものだったのを知っています。
その文字が生まれた起源としてこの記事で見てきた感覚があるのだということを知ると、古代文明の不気味な壁画や彫刻も、とても興味深いものになってきます。
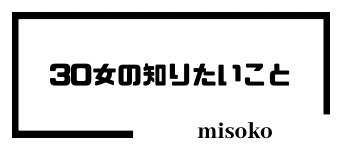



コメント